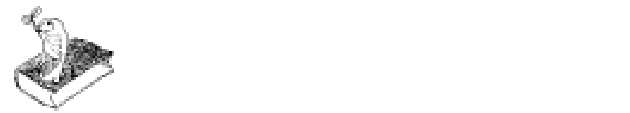この目にあなたの救いを
ルカによる福音書2:25-35
2008年12月28日
イエスさまは馬小屋の飼い葉桶で生まれました。羊飼いたちと東方の博士たちは場所に関係なくイエスさまに会うために馬小屋まで来ました。しかし、わたしたちはイエスさまに会うために綺麗で静かな場所を好んでいるような気がします。そのような矛盾のある心にイエスさまは来られたのです。
イエスさまの誕生はへりくだりの実践でした。今日の箇所でシメオンという老人はメシアを待ち望んでいます。シメオンは神と共に歩み、自分を神に委ねてイスラエルの回復を祈りながら聖霊に導かれる人です。彼はメシアに会うまでは決して死なないというお告げを聖霊にいただいていました。やがて彼は神殿に来たヨセフとマリアに抱かれたみどりごイエスに出会うのです。シメオンは赤ん坊のイエスさまを見て、すべての人のために整えられた神さまの救いを見て大いに喜びました。
シメオンが見たのはイエス・キリストの十字架だったのではないかと思います。シメオンがイエスさまのことを「多くの人を倒したり立ち上がらせたりする」と言い、マリアに「あなた自身も剣で心を刺し貫かれます」と言ったからです。パウロも「十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、わたしたち救われる者には神の力です」と証しています。十字架こそ神さまがわたしたちのために用意してくださった唯一の救いの道です。
私たちは2008年最後の主日礼拝を献げています。私たちの身代わりとなって十字架につけられたイエス・キリストの救いをシメオンと共に見て1年を振り返りましょう。
お言葉どおりなりますように
ルカによる福音書1:26-38
2008年12月21日
マリアは受胎告知を受けて、「お言葉どおり、この身になりますように」と応答します。ここで注目したいのは、マリアの応答が神さまの語りかけによってなされた、という点です。
マリアは天使から神さまに恵みを受けて神の子を身ごもることを伝えられますが、初めは戸惑いと驚きで「どうして、そのようなことがありえましょうか」と答えました。わたしたちも日々の信仰生活の色々な場面で神の御言葉に戸惑いを覚えたことがあるでしょう。
マリアは天使から「聖霊」と「いと高き方の力」が働く時にそれが可能になると言われます。そして、不妊の女だと言われていた親類のエリサベトの妊娠をも告げられます。神さまの救いの御業はわたしたちの経験や常識をはるかに超えて聖霊と神の力によって成し遂げられていくものです。私たちもマリアが応答したように、「み言葉が必ず実現する」そして「自分の身を神さまに委ねる」という信仰が求められています。
マリアはこの応答が険しい道(破婚や、姦淫の女として石打されるかも知れない道)への一歩であることを良く知っていたことでしょう。しかし、神さまは御言葉を信じて身を委ねたマリアを主と共に歩む道へと導かれ、彼女の生涯を大きく用いられました。
マリアは「主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた」(1:45)人です。クリスマスを迎えたわたしたちもまたイエスさまのご降誕を御言葉の実現として心から受け止め歩みたいものです。
私の助けはどこから来るのか
詩編121:1-8
2008年12月14日
詩編121編は巡礼者の歌です。エルサレム神殿への巡礼は私たちの人生の旅路に例えられます。詩人は1-2節で山々を仰いで「わたしの助けはどこから来るのか」「わたしの助けは来る。天地を造られた神のもとから」と自問自答します。「山々」とは神が臨在する喜びの場所でもあれば、そこに至るまでの道は試練の道でもある、という二重の意味があります。ですから、詩人は喜びと試練が交差する巡礼の旅路を振り返ってみて神さまの助けをしみじみと実感していると言えます。
詩人は3-8節で巡礼者たちに「あなたの出で立つのも帰るのも主が見守ってくださるように。今も、そしてとこしえに」と執り成しています。4節の「見よ」という言葉は巡礼者たちを巡礼の大変さや苦しさだけではなく、イスラエルの民を歴史の中で見守って下さった神さまに向わせようとする詩人の思いの詰まった呼び掛けです。「まどろむこともなく、眠ることもない」神さまは、わたしたちの人生の旅路をも見守ってくださるに違いありません。
待降節に巡礼者と言えば、東方から来た3人の博士が思い出されます。一説では博士は4人だったそうですが、4人目の博士は旅路で貧しい人々を助けたためにイエスさまの誕生に間に合わず、遅れて着いてからも幼児虐殺の嵐の中で人々を助けたそうです。4人目の博士自身はイエスさまに会えなかったと落胆していたかも知れませんが、イエスさまはすでに彼と出会い、彼と共に歩んでいたと思われます。
人生の旅路をいつも見守って下さるお方に目を向けましょう。4人目の博士と同様にイエスさまに出会っているかも知れません。
荒野で叫ぶ声
マルコによる福音書1:1-8
2008年12月7日
本日の箇所から時空を越えて神さまに用いられた3人の人物を考えてみましょう。そこから「荒野の叫ぶ声」という意味が浮かび上がると思います。
一人はこの福音書を書いたマルコで、彼はローマ帝国とユダヤ人からそれぞれ迫害されていた紀元後70年頃のイエス信仰者たちを、神の子イエス・キリストに向かわせています。もう一人は紀元前800年頃メシア(救い主)を待ち望んだイザヤ預言者で、彼は神よりも隣国の軍事力を信頼して滅びつつある人々を、メシアに向かわせています。最後の一人は洗礼者ヨハネで、彼は旧約聖書の御言葉どおり、荒野で主の道を備える者として人々に後から来るイエスさまをひたむきに指し示しています。
彼らが置かれた現実はまさに荒野だったのではないでしょうか。彼らの現実は苦難や絶望の只中にありましたが、その中で彼らの人間的信頼の対象は剥ぎ取られ、神さまの御声が心に響き渡り、神さまだけに望みをおくように強いられたことでしょう。そのような意味で荒野とは真っ暗闇に差し込む光の輝きを喜ぶ場所です。神さまは御自分の救済史の中で時に応じて人を選ばれ、イエス・キリストを叫ぶ声として用いられるお方です。
エジプトの奴隷状態から救い出されたイスラエルの民が導かれた場所は荒野でした。40年間の荒野の旅路は神さまと神の民との蜜愛の場所でした。
わたしたち一人一人が置かれている状況や、抱えている課題は異なりますが、その只中で神さまに聞き従っていきましょう。また、ひたむきに神の子、イエス・キリストを指し示していきましょう。神さまはわたしたちを荒野で叫ぶ声として用いられることでしょう。
福音に共にあずかる
コリントの信徒への手紙一9:19-23
2008年11月30日
かつて太平洋戦争末期に日本軍は「天皇のため」という旗幟を掲げて特攻隊の飛行機に若者を次々に乗せて敵陣に突撃させたことがあります。しかし、それはナショナリズムが作り上げた夢想でした。その傷が心にまだ鮮明なだけに、今日のパウロの「どんなことでもします」という言葉に戸惑いを感じるかも知れません。
はたして何がパウロに自由を放棄させ、相手の状況に自らを置かせたのでしょうか。その理由は「人を得るため」であり、「何人かでも救うため」であり、「福音のため」であります。それは「わたしが福音に共にあずかる者となるため」という一言に尽きるでしょう。
「福音に共にあずかる」とは、福音を伝える者にとっても、伝えられる者にとっても「わたしたちの罪のために死に渡され、わたしたちが義とされるために復活させられた」(ローマ4:25)イエス・キリストと共に生きることです。すなわち、キリストの十字架を仰いで、自らの罪を知らされ、かつその十字架において自分に対する神の恵みの救いが与えられている、という信仰に生かされることです。その時、福音を伝える者、伝えられる者の間にはイエス・キリストを通しての生き生きとした交わり(コイノニア)が生じるようになります。
待降節(アドベント)を迎えました。この世の偽りの価値に否を唱えつつ、いつの世代も変わらない「福音」に共にあずかるクリスマスを待ち望みましょう。
キリストを通して神に感謝
ローマの信徒への手紙7:13-25
2008年11月23日
使徒パウロは24節で「わたしはなんと惨めな人間なのでしょう」と嘆いていますが、続く25節では「わたしたちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします」と喜んでいます。この転換はどこから来たのでしょうか。
まず、パウロの嘆きは「望むことは実行せず、かえって憎んでいることをする」(15)自分の罪の性質から来ています。換言すれば、自分の中に罪の法則と霊の法則とがあり、いつも罪の法則に負けてしまう自分を嘆いているわけです。これはパウロだけではなく、わたしたちの悩みでもあります。
次に、パウロの感謝は「罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断された」(8:3)神さまの救いの御業から来ています。イエス・キリストの十字架上での身代わりの愛に対して感謝しているわけです。ここにこそ、わたしたちの悩みの解決が見えて来ます。
ルカによる福音書にはイエスさまを3度否認したペトロの話が出てきます。3度目に否認したときに、ペトロはイエスさまと目と目があって外に出て激しく泣きますが、ペトロの涙には意志の弱い自分の惨めさと、にもかかわらず自分を受け入れてくださるイエスさまへの感謝が含まれていたと思います。
わたしたちも自分自身の弱さに日々悩みますが、ありのままのわたしたちを受け入れてくださる主イエス・キリストを通して神さまに感謝して歩みましょう。
子どもたちへの祝福
マルコによる福音書10:13-16
2008年11月16日
人々がイエスさまに触れていただくために、子どもたちを連れて来たように、わたしたちも抱えている課題を自分の力で何とかしようとするよりもまずは、イエスさまのもとへもって行きたいと思います。
弟子たちはイエスさまのために子どもたちを連れてくる人々を叱りました。しかし、イエスさまはこれをご覧になり、憤ったとあります。なぜなら、弟子たちにとって子どもたちは邪魔な存在でしたが、イエスさまにとっては祝福されるべき存在だったからです。わたしたちもイエスさまの視点から物事を見たいものです。
イエスさまは「神の国はこのような者たちのものである」と言われた後、「子どもたちを抱け上げ、手を置いて祝福された」とあります。子どもの一番の特徴は純粋に物事を受け止めることですから、イエスさまは素直に神の国を受け入れることを求められているのでしょう。
このイエスさまの祝福は、子どもたちへの祝福であると同時に、やもめや孤児、病人などに代表される当時の弱い人々、虐げられている人々への祝福だったと思います。イエスさまはそのような人々のために御自身を低くされてこの世に来られました。そして弱い人々の友として生涯を歩まれ、十字架につけられました。イエスさまの祝福には、わたしたちのために命をも惜しまずに与えてくださる愛が込められています。
教会の子どもたちを含めてすべての人々がイエスさまの祝福に与っていることを覚えて日々歩みたいと思います。
主のいつくしみに生きる
列王記上19:1-18
2008年11月9日
イゼベルはアハブ王からカルメル山でバアルの預言者たちとの対決で勝利したエリヤを必ず殺すと誓います。恐ろしくなったエリヤは直ちに荒野へ逃げ、自分の命が絶えるのを願います。このエリヤの勝利に続く挫折はわたしたちの信仰の歩みに似て見えます。
神さまは絶望の中で横になって寝てしまったエリヤに触れて「起きて食べなさい」と言われ、焼きたてのパンと水を食べさせます。神さまは「なぜ恐れるのか」とエリヤを責めるのではなく、2回も「起きて食べなさい」と優しくエリヤを励まされたのです。この神さまのいつくしみに力づけられてエリヤは四十日四十夜を歩いて神さまの山ホレブに着きます。そこでエリヤは主の前に立たされて静かにささやく主の声に耳を傾けます。神さまはエリヤに、油を注いで王と後継者を立てるようにと命じられます。これは神さまの働きがイスラエルの歴史の中で今までと変わらずに続けられることを意味しています。
エリヤは情熱を持って神さまに仕えて来たのですが、どこか自分の力でそれを続けてやり遂げようとしたために、それが出来なくなった時に絶望の淵に陥ったのです。しかし、神さまはエリヤを励まされ、イスラエルの歴史を支配しておられるご自分の働きの中で、一つの道具としてエリヤを用いようとされたのです。
わたしたちも常に神さまのいつくしみに励まされ、神さまの働きに用いられることを喜びながら日々歩みたいと思います。
人生の年輪
コラム
2008年11月2日
木には年輪があります。年輪は毎年一層ずつ重なり、同心円の模様はそれまでの木の人生を物語ります。人も人生の年輪を持っています。幸福な人生の春や、厳しい試練の冬を通り抜けての各々の模様は、過去から現在までの自分を物語り、未来の自分を形づくる基礎となります。
先週、関田寛雄先生をお迎えして土・日曜日と二日間特別伝道集会を行いました。私は先生のお話の中でザアカイとパウロの人生の年輪を垣間見ることが出来ました。ザアカイは誰にも受け入れてもらえませんでしたが、ありのままの自分をすべて受け入れて下さるイエスさまと出会い、心に正義と愛とが芽生えました。パウロはキリスト者への迫害に熱心でしたが、ダマスコの途上でイエスさまと出会い、ユダヤ人から迫害されキリスト者からはうたがわれながらも福音伝道に励みました。二人の人生の年輪にはイエスさまとの出会いがしっかり刻み込まれていて、そこから新たな人生の年輪を重ねていったと思います。彼らの年輪の模様は時空を超えてわたしたちに力と勇気を与えてくれます。なぜなら、彼らを受け入れてくださり、用いて下さった神さまの恵みがそこには残されているからです。
今、わたしたちが置かれている状況は様々かもしれませんが、わたしたちの人生の年輪に描き出される主の憐れみはきっと人々に慰めを与えることでしょう。「あなたがたの中で善い業を始められた方が、キリスト・イエスの日までに、その業を成し遂げてくださる」(フィリピ1:6)ことを確信して日々歩みたいと思います。
わたしは命のパンである
ヨハネによる福音書6:41-51
2008年10月26日
不慮の事故に遭って手足の自由を奪われた星野富弘氏は「こんな自分が生きていいのか」と自分のみじめさに苦しみますが、信仰に導かれて永遠の命であるイエスさまに出会ってからは「このけがには意味がある」と考えるようになり、生きるのが喜びになりました。
わたしたちがもし人生の中で埋められない飢えや渇きに苦しむのなら、「わたしは命のパンである」と言われたイエスさまに聞きましょう。イエスさまに来る者、すなわちイエスさまを心から受け入れる者は「決して飢えることなく…決して渇くことがない」とイエスさまご自身が約束してくださっているからです。どうすればそれが可能となるのでしょうか。
まずは「わたしをお遣わしになった父が引き寄せてくださらなければ、だれもわたしのものへ来ることはできない」ということを認めることです。それは神さまの愛の支配を体験させられる形で「神によって教えられる」事柄だからです。神さまは御自分の独り子をこの世に送られてイエスさまを信じる者がみな、永遠の命を得るようにと望んでおられるお方です。また、イエスさまに与えられた人々を一人も失わず終わりの日に復活させるようにと望んでおられるお方です。イエスさまの十字架と復活を通して示された神さまの愛に目を向けさせられる時、命のパンであるイエスさまを信じるようになります。
「いのちが一番大切だと思っていたころ 生きるのが苦しかった。いのちより大切なものがあると知った日 生きているのが嬉しかった」と星野氏が詠っているように、命のパンである主イエスに変えられていくことを祈ります。
*星野富弘(1946~):口に筆を取って作品創作する詩人・画家
二つの招待
箴言9:1-18
2008年10月19日
ウィリアム・シェイクスピアの4大悲劇の『ハムレット』の「生きるべきか死ぬべきか」という台詞は、観衆に「自分の存在をかけて生きる道とは何か」という問いを投げかけています。神さまは私たちがどのように生きることを望んでおられるのでしょうか。
今日の箇所には知恵夫人と愚か夫人の対照的な招きが出てきます。知恵夫人は七本の柱のある家、パンと調合した酒などで整えられた祝宴を準備して人を遣わして人を呼ばせます。人を遣わす知恵の正体は分かりづらいと思いますが、知恵に招かれた人は命を得、分別の道を進められます。一方、愚か夫人は何の準備もなく遊女のように門口に座って語りかけています。呼びかけられる人が「自分の道をまっすぐに急ぐ人々」であることから、普通の人が愚かさに招かれていると思いますが、愚かさに招かれた人は深い陰府に陥ります。二つの招待に目的地は示されていますが、道筋は不明な印象を受けます。
しかし、私たちは「主を畏れることは知恵の初め、聖なる方を知ることは分別の初め」(10)という言葉からその道筋を教えられるのではないでしょうか。「主を畏れること」は、神さまが裁きを正しく行われる(公義)ことを信じて御心に従うことです。また「聖なる方を知ること」は、唯一である神さまとの交わりを通して神の愛(憐れみ)に気付かされていくことです。
主を畏れつつ、主の愛を知っていく生涯を生きた人は十字架上で御自分の命を献げて下さったイエス・キリスト唯お一人です。わたしたちはイエス・キリストが共にいてくださるから、信仰の歩みができるのです。
失われた息子
ルカによる福音15:11-24
2008年10月12日
ルカによる福音書15章に出てくる三つのたとえ話は(見失った羊、無くした銀貨、失われた息子)、徴税人や罪人と交わりを持っているイエスさまに不平を言うファリサイ派の人々や律法学者たちへイエスさまの答えです。主題を一言で言えば、喜びへの招きです。
ある人に二人の息子がいます。弟は父に反抗して父のもとを離れます。他国で放蕩の限りを尽くし、財産を無駄使いしてしまいには豚の世話をする苦境に陥ります。しかし、我に返って父の家の豊かさを思い出し、そこを発ち父のもとに帰って行きます。そして「息子を見つけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻」する父親に再会します。息子は自分の過ちを告白し、雇い人となることを望みますが、父は息子が「死んでいたのに、生き返り、いなくなっていたのに見つかった」と大いに喜びます。失われた息子の帰郷に父が喜び祝宴を開きますが、いつも父親に仕え一度も背いたことのない兄は、祝宴に入らず、怒って外にいます。兄は父親のそばにいながら失われた息子だったかも知れません。父親は出て来て兄をなだめます。兄にも喜びに参加して欲しかったのでしょう。
イエスさまと共にいた徴税人や罪人は弟です。それに不平を言うファリサイ派の人々や律法学者たちは兄です。イエスさまは両者共に神さまの子であることに変りないことを告げると同時に、神さまのもとに立ち返る者を喜ぶ主の喜びに参加することを望んでおられます。
私たちは誰もが神さまの子です。時には見つけるまで探し出す、時には待ち続ける主の喜びを一緒に喜んで歩みましょう。
神に造られた私
創世記2:4b-9
2008年10月5日
「主なる神が地と天を造られた」(4b)という言葉は、天地生成の経過の説明であるよりは、神さまが万物の根源であり、神さまは「アルファであり、オメガである。初めであり終わりである」(ヨハネ黙示録21:6)と告白することです。
創世記には二通りの天地創造の物語があります(1:1~2:4b&2:4~3:24)。2:4b以下の創造物語は、雨がなく「野の木も野の草も生えていない」乾いた印象ですが、1章の創造物語は「神の霊が水の面を動いていた」と潤った印象を受けます。この差は二つの創造物語が編集された時代の状況が違うからです。2章はダビデ王朝の時代にパレスチナを背景に、1章はバビロン捕囚の時代にチグリス・ユーフラテス川を背景にしています。国の全盛期に高ぶることなく、衰退期に絶望することなく、イスラエルの民は創造主への信仰を持ち続けて来ました。
2章では人間を、7節に「主なる神は、土の塵で人を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた」とあるように、人間は必ず土に帰るはかない存在である反面、神さまの命の息を吹き入れられた尊い存在であることを見極めていました。まさしく死と永遠の命を念頭に置いた生き方を目指し、神さまにエデンの園を「耕して、守るようにされた」(15)ように置かれた状況の中で最善を尽くす存在であると考えていたのでしょう。創造主への信仰告白は自分の力や所有を手放して、神さまの主権の下に御言葉に聞き従う決断をすることではないでしょうか。
「神に造られた私」たちは人間の限界性と永遠性との緊張の中で創造主を告白し、また服従して日々歩んでいきましょう。
真の豊かさ
ルカによる福音書12:13-21
2008年9月28日
権力と名誉の頂点を生きた伝道者はコヘレトの言葉の1章で「すべて空しい」と人生を懐疑しますが、締め括りの12章で「お前の創造主に心を留めよ」と切に願っています。これは競争・格差社会に生きるわたしたちにとって示唆に富んでいる言葉だと思います。私たちは「豊かさ」を所有として考えがちですが、聖書は「豊かさ」を新しい次元で語っています。
群衆の一人がイエスさまに遺産相続の調停を求めますが、一言で断られます。イエスさまは人々の関心を「貪欲」から「人の命」へと移され、愚かな金持ちの譬え話を話されます。
畑の豊作で倉が狭いことを心配した金持ちが打ち出した妙案は倉を大きく建て直すことでした。そして自分の蓄えに陶酔して食べよう、飲もう、楽しもうと自分のたましいに言い聞かせます。金持ちの姿はわたしたちの中に潜んでいる自画像かも知れません。所有を喜んでいた金持ちは神さまに死という実存的な問いを突きつけられます。それは、人生は儚いものである、富は永遠のものではないという問いでもあります。
物を持つこと、物を与えられることには確かに喜びがあります。しかし、それは神の前で豊かになることではありません。「神の前で豊かになる」とは与えることを喜び、自分を犠牲にすることを喜ぶことではないでしょうか。
与えられることを喜ぶ信仰から与えることを喜ぶ信仰へと成長し、「真の豊かさ」に目覚めて歩みたいと思います。
渇かない水
ヨハネによる福音書4:7-15
2008年9月21日
今日の箇所に出てくるサマリアの女は様々な心の傷を負っていたと思われますが、イエスさまとの思いがけない出会いを与えられ、イエスさまとの対話の中でイエスさまがメシアであること、また自分のたましいの渇きに気付かされます。その結果、サマリア地域伝道の福音の種となる、かけがえのない人生へと変えられていきました。
イエスさまは社会的通念、歴史的常識をはるかに超えてサマリアの女と接してくださり、彼女を神さまの賜物、すなわち、イエス・キリストご自身に招きます。彼女はイエスさまの招きに戸惑い、「どうして」「どこから」という疑問を連発しますが、イエスさまは「わたしが与える水を飲む者は決して渇かない。…永遠の命に至る水がわき出る」と言われます。これはイエスさまが十字架上で流して下さった血潮によってわたしたちに永遠の命が与えられたことを意味しています。わたしたちは命さえも惜しまず与えてくださるイエスさまをすべて理解できませんが、それを必死で求めた彼女の姿から多くのことを教えられます。イエスさまと彼女との間の溝は確かにありましたが、彼女は自分の疑問を率直に出し、イエスさまがそれに誠実に答えられることによって、次第に彼女はイエスさまがメシアであること、また自分の中に潜んでいた主なる神を礼拝するという魂の渇きにも徐々に気付かされていきました。
私たち教会もこの世の中で渇く水を求めるのではなく、渇かない生ける水であるイエス・キリストをひたむきに求めていきたいです。
モーセの執り成し
出エジプト記32:7-14
2008年9月14日
イスラエルの民は「主が語られたことをすべて、行います」(出19:8,24:3)と言いましたが、直ちに主が「命じた道からそれて」しまいます。モーセがいない間、若い雄牛の鋳造を造ってこれを「エジプトの国から導き上った神々だ」と叫んでいます。
これに対して神さまは怒りを燃え上がらせます。民を滅ぼし尽くす勢いです。神さまは十戒で偶像崇拝を戒めながら「わたしは主、あなたの神、わたしは熱情の神」(出20:5)と言われます。ここで「熱情の神」とは「妬む神」と同義語です。神さまは私たちを妬むほど愛して下さるお方です。迷子となった子どもを見つけた親は子どもに怒りますが、その怒りは子どもに対する愛があるがゆえに出てくるもので、子どもは親の愛を感じるはずです。神さまの怒りから見えてくるものは神さまの限りない愛です。
神さまの怒りの前にモーセは執り成しの祈りを献げています。イスラエルの民が神さまによって導き出された神さま御自分の民であること、また神さまの怒りがエジプト人に嘲笑われることを神さまに訴えています。そして、神さまがアブラハム、イサク、イスラエルと結ばれた祝福の約束を思い起こすようにと切に祈っています。モーセの執り成しから私たちは神さまの約束にすがり付く祈りを教えられます。
真の仲介者は、神の前に立って私たちのために執り成しておられるイエス・キリストであります。わたしたち教会は、常にこの十字架のキリストを指し示して歩んでいきましょう。
立て、行こう。
マルコによる福音書14:32-42
2008年9月7日
最後の晩餐が終わり、イエスさまと弟子たちはオリーブ山へ出かけました。イエスさまは十字架の苦難を控えて弟子たちと共におられ、弟子たちに祈るように言われました。
イエスさまは死ぬばかりに悲しみながら十字架の苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈りましたが、最後には神さまの御心に適うことが行われることを願いました。自分の願いよりも神さまの御心を大切にしました。
イエスさまは弟子たちに誘惑に陥らずに目を覚まして祈るように言われましたが、弟子たちは疲れのあまり何度も寝てしまいます。わたしたちはこの弟子たちの姿に自分の弱さを痛感させられます。しかし、そのような姿にもかかわらず、イエスさまはわたしたちのすべてをそのまま受け入れて下さり、「立て、行こう」と言われるのです。「立て、行こう」という言葉は途方に暮れていた弟子たちに勇気を与えたことでしょう。私たちも同じく勇気を与えられます。イエスさまは師の死を前にして居眠りしてしまった弟子たちのようなわたしたちと共に歩みたいと「立て、行こう」と手を差し伸べて下さっています。ここにこそ私たちが感謝する理由があります。
毎週の礼拝後、私たちはそれぞれの生活の場へと繰り返し派遣されています。わたしたちはいつも失敗を繰り返して途方に暮れますが、主イエスはそのような弱い私たちを「立て、行こう」と招いて下さいます。恵みと慰めに富んだ言葉を覚えて日々歩みましょう。
キリストに贖われた教会
ヘブライ人への手紙9:23-28
2008年8月31日
キリストは教会の頭であり、教会はキリストの体であります。両者を切り離して考えることは不可能です。なぜなら、教会はキリストに贖われたからです。イエスさまの時代には、毎年1回大祭司が神殿の至聖所に入り、動物の犠牲によって罪が赦されるという贖罪日がありました。これは出エジプトの時、神さまが羊の血が塗られている家を過越された出来事に由来します。
ヘブライ人への手紙の著者はこのような犠牲儀式を守っているユダヤ人に対して、イエス・キリストがまさしく「神の小羊」としてこの世に来られ、御自身をいけにえとしてただ一度献げられ、世の罪を取り去られたことを宣べています。それゆえ、イエス・キリストは他の動物の血を携えて神殿に入る大祭司にまさります。また、キリストは天の模型である幕屋ではなく、天そのものに入られて神さまの前に立たれました。これによって、キリストは人々の罪を取り除かれ、救いを与えてくださいました。
ユダヤ人の儀式と対比させながら述べられている「ヘブライ書」のイエス・キリストの救いの業には、御自分を低くされた「受肉」と神さまに高く挙げられた「復活」が秘められています。人間はいつも高ぶり神のように振舞うのですが、キリストは逆に徹底的に御自身を低くされました。人間は自分の力ではどうしても罪から立ち返ることの出来ない者ですが、「イエスは主である」と告白する者には救いが与えられます。
わたしたちの救いは自分の感情や、意志にものではなく、イエス・キリストが御自身をいけにえとして献げられことによるものです。このことに信頼を置いて歩みましょう。
主の慈しみに生きる
詩編32:1-11
2008年8月24日
「慈」という字は「小さい芽を育てる」という意味から「小さい子を育てる親心」を表しています。作物を栽培する農夫の心や、子どもを育てる親心は、愛情に満ちています。「慈しみ」は「愛しみ」、「厳しみ」とも書きます。「主の慈しみに生きる」とは、農夫や親のように私たちの人生に関わり続けて下さる主の恵みの内に歩むことにほかありません。
詩編32編には神さまと私たちの関係を意味づける二つのキーワードがあります。一つは「赦し」(1-5節)であり、もう一つは「信頼」(6-11節)です。詩の冒頭で詩人は「いかに幸いなことでしょう」(1-2節)と喜びの声をあげています。なぜなら、自分の背きを神さまに赦されたからです。神さまの赦しは、神さまご自身が私たちの罪を引き受け、その代価を払って下さるという神さまの恵みによるものです。私たちはイエス・キリストの十字架の前に立つ(=自分の罪を告白する)ことで、神さまの一方的な恵みを受けるのです。
神さまの赦しによって、人間の背きのために途絶えていた神さまとの関係が回復され、新しい信頼関係が築かれます。詩人はその赦しを根拠に主に祈り、主を避けどころとし、主に導かれることを詠っています。
主に対する背きが神さまに赦され、破れていた神さまとの信頼関係が回復された私たちの歩みは主の慈しみに囲まれているのです。主の慈しみに囲まれることは、神さまに赦され、神さまを信頼していく人生です。わたしたちも農夫や肉親のような神さまの愛によって育てられていきたいものです。
主のもとへの招待
マタイによる福音書11:25-30
2008年8月17日
「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう」
私たちに休みを備え、安らぎを与えて下さるのはイエス・キリストです。イエスさまは「わたしのもとに来なさい」と私たちをイエスさまご自身に招かれます。なぜでしょうか。イエスさまは「柔和で謙遜な者だから」と言われています。「柔和」とは重荷を負わされ、虐げられているがゆえに、人の弱さや悲しみを理解できる人のことです。「謙遜」とはへりくだった人のことです。イエス・キリストは十字架の死に至るまで重荷を負い、低くされたお方であるからこそ、私たちの苦しみ、重荷を深く理解し、私たちに安らぎを与えることが出来ます。
主の招きは、イエスさまが私たちから重荷を取り去って下さるから安らぎを得られると言ってはいません。代わりに「わたしのくびきを負い、わたしに学びなさい」と呼びかけられています。これは、「自分の十字架を背負ってわたしに、従いなさい」という呼びかけでもあります。私たちは一人で自分の重荷を負っているのではありません。イエスさまが共にわたしの重荷を担って下さっています。教会や人生の重荷、課題を担って生きる時に、キリストご自身が必ず共に重荷を背負ってくださるから、キリストのくびきは負いやすく荷は軽いのです。
今朝、イエスさまはご自身も十字架に至るまで重荷を背負い、苦難を受けたゆえに、柔和で、心のへりくだった者であるから、わたしのもとに来なさいと招かれています。
平和の王
イザヤ書9:1-6
2008年8月10日
「平和」とは旧約聖書のヘブライ語「シャローム」の訳です。戦争のない状態だけでは無く、人間同士や、人間と神さまとの関係に欠けや歪みがない十全な状態を意味しています。この「シャローム」は、人間が作り出すものではなく神さまから来るものです。
前730年頃のイスラエルは、かつての全盛期を過ぎて国は南北に分裂し、北王国はアッシリアに滅ぼされ、南王国も存亡が危ぶまれました。多くの人々が戦争の悲惨さに巻き込まれていきました。その只中でイザヤ預言者は「シャローム不在」の現実から神さまの裁きを見ながら、その先にある神さまの「シャローム」、すなわち、神さまの熱意によってイエス・キリストを通して持たされる平和を見ていたのです。
当時の人々は列強国の力をかりて平和を造ろうとしたのですが、それに対して預言者は神さまから来る平和を語ります。神さまは正義と恵みの業によって平和を立てられ支えられます。その平和は今からとこしえに絶えることがありません。なぜなら、神さまの熱意が必ずこの平和を成し遂げられるからです。預言者が5-6節で見ていたシャロームはイエス・キリストの生涯、また死と復活において実現されました。神さまの平和は人間にまで身を低くされ、傷つけられた者の傍らで共に歩まれたイエスさまが無力な姿で十字架に架けられた出来事によって明らかにされたのです。
偽りの平和ではなく、イエス・キリストの十字架に現された神さまのシャロームを受け止め、語り継いでいきたいと思います。
信仰に踏みとどまる
ペトロの手紙一5:8-11
2008年8月3日
今日の箇所はペトロが諸教会に宛てた手紙の結びの言葉です。ペトロは信仰にしっかり踏みとどまること(8節)、そして、神さまご自身が人々を揺らぐことがないようにして下さる(11節)という信頼を語っています。ペトロの信頼はどこから来たのでしょうか。ペトロはイエスさまとの体験を思い起こしたのでしょう。
一つは、徹底的に失敗した体験です。イエスさまの死の直前、ペトロは「たとえ、みんながあなたにつまづいてもわたしは決してつまづきません」と答えますが、その夜ペトロはイエスさまを三度も知らないと否認します。生涯忘れることの出来ない失敗です。ペトロはその心の傷を抱えたまま漁師に戻ったのです。もう一つは、イエスさまによって回復させられた体験です。絶望に陥りガリラヤに戻ったペトロに復活されたイエスさまが近寄ってこられました。イエスさまはペトロと共に食事をしてから「わたしを愛しているか」と三度聞かれます。ペトロは「愛しています」と三度答えます。このやりとりの中でペトロの心の傷が癒されていったのでしょう。イエスさまはもう一度「わたしに従いなさい」(ヨハネ21:19)と呼びかけられ、ペトロは失敗を乗り越えて証人として生きていったのです。
わたしたちもペトロの勧めに耳を傾けたいものです。信仰にしっかり踏みとどまりましょう。自分の力では出来ません。イエス・キリストを通して永遠の命へと招いて下さる恵みの神さまご自身がわたしたちを完全なものとし、また、揺らぐことがないようにして下さいます。
わたしは主によって喜ぶ
ハバクク書3:17-19
2008年7月27日
ハバククは覇権主義の力の中心がアッシリアからバビロンに替わる時代を生きた預言者です。彼はその中で滅びに向かう南王国を嘆きながら、「正義はいつまでも示されない・・・・黙っておられるのですか・・・・彼らは諸国民を殺すために剣を抜いてもよいのでしょうか」と神さまに訴えています。
これに対して神さまは「彼らは罪に定められる。自分の力を神としたからだ」とバビロン帝国の滅びを約束され、また「それは必ず来る、遅れることはない・・・・神に従う人は信仰によって生きる」と預言者を励まされます。
預言者は祈りの対話の中で自分の疑問や嘆きを神さまにぶつけますが、神さまは預言者を出エジプトの出来事に向かわせます。その時はじめて、預言者の疑問や嘆きは主にあっての喜びと讃美へと変えられたのです。このことによって預言者は収穫が全く無い状況(17節)の只中で、神さまの正義は必ず行なわれるという信頼を持たされました。そして18節で「しかし、わたしは主によって喜び、わが救いの神のゆえに踊る」という告白に至っています。
イエス・キリストの十字架上での死もまた理不尽な出来事でした。しかし、神さまは私たちを十字架という極刑の中に示された神さまの恵みに向かわせます。それは独り子をこの世に渡された神さまの一方的な恵みです。その時はじめて、私たちの疑問や嘆きはイエスさまの復活の希望へと変えられていくのです。
神さまの正義を信頼しつつ、主によって喜び踊る日々の歩みとなればと思います。
何をしてほしいのか
マルコによる福音書10:46-52
2008年7月20日
神さまは若者のソロモンに「何事でも願うがよい。あなたに与えよう」(列王記上3:5)と言われます。ソロモンは知恵を求め、神さまはソロモンに知恵の満ちた賢明な心を与えられます。ソロモンは主の心に適ったものを求めたと思います。
今日の箇所でも、イエスさまは目が不自由で物乞いのバルティマイに「何をしてほしいのか」と言われます。彼は人々に叱りつけられながらも、諦めずに憐れみを求め続けました。イエスさまの問いに対して、バルティマイは一切のためらいもなく、「見えるようになりたいです」と答えます。すると、イエスさまは「あなたの信仰があなたを救った」と彼の救いを宣言され、すぐ視力が回復されたバルティマイはイエスさまに従います。バルティマイは肉の目は不自由でしたが、イエスさまが自分を救って下さるメシアであることを見ていました。
実は、この「何をしてほしいのか」という問いは、36節で二人の弟子たちにもされています。しかし、二人の弟子は「私どもをあなたの左右に座らせて下さい」と答えています。二人はイエスさまの苦難と復活の予告(32-34節)を勝手に革命の勝利として捕らえていたようです。肉の目は何の不自由もなかったが、イエスさまの真実の姿が見えていなかったのです。
目が不自由だったのは誰だったのでしょうか。イエスさまは今日のわたしたちにも「何をしてほしいのか」と言われています。「あなたの十字架の死と復活の恵みが見えるようになりたいです」と答える信仰を祈り願います。
沈黙の叫び
詩編62:6-7
2008年7月13日
詩編62編の詩人はたましいとの深い対話の中で、耐え難い現実から希望を見出し、揺るがされることはないと確信しています。
詩人は6節で「沈黙して、神さまに向え」と自分のたましいに呼びかけています。この「沈黙」には、忍耐して待ち望むという意味があります。詩人は自分が置かれている現実を乗り越えられるという希望を神さまにのみおいています。この詩は息子のアブサロムの反逆を避けて逃亡者となり、命の危険を抱えているダビデによって詠われたものだと言われています。愛する息子からの裏切りや身に迫る危機という現実の厳しさの中で、詩人は神さまだけに目を向けています。
詩人は主に向うことにより現実に向き合う力を得ています。そしてそれが繰り返し行われています。その中で、詩人は神に信頼し、神さまに心を注ぎ出すように呼びかけています。そして、「神はわたしの岩、わたしの救い、砦の塔」だと告白し、揺るがされることはないという信頼に満ちています。なぜでしょうか。それは力と慈しみが目に見える人や権力にあるのではなく、ただ歴史を支配する神さまにのみあることに気付かされたからでしょう(12-13節)。それは唯一の神さまが正しく報いを与えて下さるという信頼でもあります。
それぞれ置かれている現実から沈黙して神さまに向いましょう。神さまはわたしたちを守って下さいます。その方に心を注ぎ出しましょう。揺るがされることはないという信頼をもって歩みましょう。
一つの体の部分に優劣なし
コリントの信徒への手紙一12:14-26
2008年7月6日
教会はキリストの血によって贖われた、キリストに結ばれた共同体です。換言すれば、教会はキリストを頭とする一つの体であります。今日の箇所は分裂寸前のコリント教会の人々に対して、教会の多様性と一致、そして教会のあり方を人間の体と各部分にたとえて書かれたパウロの手紙です。
第一に、14節に「体は、一つの部分ではなく、多くの部分から成っています」とあるように、教会には多様な人々がいます。他人と比べて自分は立派な奉仕が出来ないと劣等感を覚える人に対してパウロは神さまが「御自分の望みのままに」一人一人を教会に置いたことに目を向けさせます。
第二に、20節に「多くの部分があっても、一つの体なのです」とあるように、教会の多様性はキリストを中心としての一致のためにあります。各個人は与えられた賜物を用いて教会に仕えて全体の益となるために務めます。他人を判断してあの人は必要ないと優越感を覚える人に対して、パウロは神さまが「見劣りのする部分をいっそう引き立たせて」教会に調和を与えられたことに目を向けさせます。
第三に、24節に「一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです」とあるように、キリストの体である教会は多様性と一致のバランスを取りながら、「共に苦しみ、共に喜ぶ」共同体です。
キリストの体である教会につらなる私たちには優劣がありません。お互いの多様性と一致を大切にしながら、共に苦しみ、共に喜ぶ教会として歩んでいきましょう。
神の力によって
コリントの信徒への手紙二6:1-10
2008年6月29日
開拓の時からパウロが深く関わったコリント教会は、パウロがいなくなった途端にパウロを嫌う人々の教えに惑わされます。パウロの敵対者たちはパウロの使徒の資格を疑うように人々を煽り立てて、中にはパウロを厳しく批判する者も出てきます。
実際、何の推薦状も持っていないパウロですが、霊的な親の気持ちでコリント教会の人々に自己推薦をしています。今日の箇所は二つに分けられます。前半では、神さまからの恵みを無駄にしないようにと勧めています。救いは律法を守る人間の努力によって得られるものではなく、罪のないイエスさまを「わたしたちのために罪となさ」った神さまの恵みによってのみ与えられるものです。パウロは再度コリントの人々を「今こそ、救いの日」と神さまの救いに向わせます。後半では、パウロ自身の伝道旅行から体験した恵みを分かち合っています。パウロは5章の後半でキリストを通して私たちに救いを与えられた方が和解のために奉仕する任務をお授けになったと強調しています。その任務を全うする中で経験した様々な苦難や欠乏などを(4-5節)、神さまの力と義の武器を持って耐え忍び(6-7節)ました。そこから「物乞いのようで、多くの人を富ませ、無一物のようで、すべてを所有しています」と恵みを分かち合っているのです。
わたしたちは土の器に宝を納めている者です(IIコリント4:7)。弱いようで、実は主にあってすべてを所有しています。その豊かさを疎かにせず、神さまの力によって日々歩みたいと思います。
豊原奏さんの証
主日礼拝にて
2008年6月22日
昨年秋まで5年間に渡りドイツのフライブルクという街で音楽留学をしてきたわけですが、僕たちにとって本当に良い学びのときであり、出会いの時であり、苦難の時でありました。
歌の先生をまだ見つけていなかった僕のスタートは、良い歌の先生がいないかという情報を友達から集めることでした。ドイツに渡って半年が経とうとすることに、やっとたどり着いたのは音大の教授を引退されプライベートレッスンをしているという70歳を超えたソプラノの先生でした。
エーファ先生というその方は本当にパワフルで、明るく、僕はこの先生との出会いが本当に嬉しく、当時も今もいつもこの出会いに感謝しています。それまでにも10年以上歌を学んできたわけですが、エーファ先生のように詳しく、しつこく、厳しく教えてくれた人はそれまでにはいませんでした。できるまで同じことを20回でも30回でも繰り返し教えられ、僕の質問に対しても本当に具体的に、また感覚的に、科学的にも説明してくれて、レッスンのひと時、ひと時が宝物のように感じられました。
しつこく繰り返し教えるとか、分かってもらえない相手に説明しつづけるということは、想像を絶するぐらいのエネルギーを必要とし、本当に分かってもらいたいという志がないとできないことだと思います。僕はレッスンを通して、いつも先生からの愛を感じました。僕がまぁまぁ良いと思ったときでも、先生は僕のまずいところを見逃さず指摘するのですが、最初はどこが悪いのかも分からず、先生の視点というものが僕には理解できませんでした。しかし歌のレッスンをテープに録り聞き返してみると、やはり先生の指摘は正しいのです。主観的に歌っていると気づかない自分の弱点が、客観的にテープを通して聴いてみると、先生の指摘の通り、はっきると見えてくるのです。
先生が最後まで僕に言い続けたことが今でも心に残ります。歌は喉で歌うものではなく体全体で歌うものだということです。「KANADE、あなたの声はとてもいいけど、あなたは体全部を使っていない。あなたはまだ30パーセントしか自分を出し切っていない」ということをよく言われました。体全体を使って歌うということは、一般的に誰もが言うことなのですが、先生のレッスンを通して、僕は自分の歌だけでなく、自分の生き方などにも通じていることだなと感じさせられました。自分の体全部を使って、自分のありったけの精神を込めて、100パーセント自分を歌で表現しなさい、という教えとして僕は受け止めました。
自分の全てを人前で曝け出すということは本当に怖いことだと思います。自分の弱い部分、嫌な部分、良い部分、その全てが歌に出てしまいます。聴いている人たちが受け止めてくれるだろうという信頼をしなければ、到底できることではありません。自分を曝け出す、100パーセント自分を表現するためには、まず相手を信頼することから始めなければいけないということに初めて気づきました。
このような出来事を通して僕はやはり聖書の教えに帰っていくような気持ちにさせられます。神様を信頼して、自分のありのままの姿で神様に仕えるということです。また、ありのままの姿でいる隣人を受け入れていくということです。その全ては信頼から来るんだということを教えられました。
僕たちが困難な状況にあっても、あきらめることなく二人で留学生活を全うできたのは、東京北教会の皆さんの祈り、またそれを聞き届けてくださった神様の恵みによるものだと思っています。
相変わらずといっていいほど、今後の見通しが立っていない僕たちではありますが、感謝しつつ歩んで生きたいと思っています。この気持ちをそのまま讃美にしたいと思いますので、心を合わせてお聞き下さい。
豊原さやかさんの証
サロンコンサートにて
2008年6月21日
ただいま、お聴きいただきました曲は、スペインのチェリスト、ガスパール・カサドという人が作曲した、無伴奏のチェロ組曲です。カサドは、カザルスというチェリストのお弟子さんでした。カザルスというチェリストはもしかしたら皆さんも耳にされたことがあるかもしれませんが、偉大なチェリストであると同時に平和活動家としても有名で、音楽を通して世界平和のために活動した人でした。
さて、私のことを皆さんに知っていただくために、これから少しお話をさせていただきたいと思います。
私はクリスチャンファミリーに育ち、小さな頃から教会に通い、そして幼い頃に洗礼を受けました。幼い私が洗礼を受ける時に信仰告白として取り上げた聖書の言葉は「神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じるものが一人も滅びないで永遠の命を得るためである」という箇所です。その頃の私は、自分の中にある罪というものを理解していたわけでも、自分の為にイエス・キリストが十字架にかかってくださったということを実感として持っていたわけでもなかったと思います。でも漠然と、大事な一人子イエス・キリストを私たちにおくってくださったほどに私を愛してくださり、何かあたたかい大きなものにいつも包まれているそんな存在として、神様を感じていました。
そんな私が中学生になり、将来のことについてもいろいろ悩む年頃に、チェロという楽器に出会いました。ロシアのモスクワ交響楽団という、大きなオーケストの演奏を大きなホールで初めて生で聴いたのです。その時の弦楽器の響きに感動し、演奏会の帰り道に興奮しながら母に「チェロをさせて欲しい」とねだったのを覚えています。母も熱しやすくて冷めやすい私の性格を見抜いていて、「その興奮が一週間冷めなかったら考えてみよう」と言いました。その一週間、私の中でチェロを弾いてみたいという気持ちが冷めるどころか、どんどん大きくなり、そして、チェロを始める事ができたらプロを目指そうとまで考えたのです。そんなわけで、チェロを始める事になった私は毎日頑張って練習し、大学にもなんとか無事に合格しました。
でも大学に入って周りを見るとみんな小さな頃から英才教育をうけた優秀な音楽家の卵達ばかりで、チェロを始めて3年ちょっとの私はとても気後れしてしまいました。そして、常にコンプレックスを感じ、「私はチェロを始めたのが遅いから・・・」という言い訳をしながら人前で弾く事の恐怖を抱いてしまっていました。
そんな焦ってばかりの私をみて、当時のチェロの先生が、私にこう言いました。「今のさやかにはテクニックはないけれど、テクニックというのは、こう弾きたい!という音楽があってこそ、付いてくるものなんだよ。例えば、君は神様を信じているんだろう?その、神様に感謝する時、その思いが強ければ強いほど、いろんな言葉や行動でもって、その感謝を表そうとするだろう?音楽も同じで、まず音楽に感動し、こんな美しい音楽をしたい、またはこんな思いでチェロを弾きたいって思えば思うほど、今の自分に足りないテクニックが見えてくる。そんなチェロでの表現方法を少しずつ学んでいけばいいんだよ」と。
周りばかり見ていた私は、あぁそうだった!こんな私のことをも心に留め、そして1人子下さったほどに愛してくださる神様がいることを知っている。そして、その神様が私にも未熟ながらのタラント、賜物を与えてくださった。私はこの賜物を小さいからといって怯えて地に埋めたままにしてはいけない、自分なりに努力をしてその賜物を少しでも大きくしたら、神様はその賜物を何倍にもして用いて下さることを信じ、自分なりの1番よいものでもって賛美していこう!と思ったのでした。
私達夫婦は去年の9月、5年間にわたるドイツでの留学生活を終えて、日本に帰ってきました。そして、これから音楽家として日本で活動をしていこうと思う中で、やっていけるのかという不安がないわけではありません。思えば、神様の愛に気づかされてからも不安になったり自信をなくしたりして自己嫌悪に陥ったりと恥ずかしながらも相変わらず繰り返しているのですが、いつも、与えられた事を自分なりの1番よいものになるように準備し、あとは神様に委ねていこうと思っています。
これから演奏します曲はドイツの作曲家ベートーヴェンの作った声楽曲で「Bitten」という曲です。「Bitten」というドイツ語は「願い」という意味で、このような歌詞で歌われています。「神様、あなたの大きな恵みは私達を満たし、あなたは憐れみをもって私達に祝福を授け、私達を助けてくださる。あなたは私のとりでであり、私の岩であり、また私の宝です。私はあなたの前で祈ります。祈りますからどうぞ、私の言葉を聞き入れてください」
十二人を派遣する
マルコによる福音書6:6後-13
2008年6月15日
十二人の弟子は、まずイエスさまのそばでイエスさまに学びました(3:14)。彼らは、イエスさまがユダヤ社会の中で罪人だと決め付けられて、すべての関係から排除されていた弱者(孤児や寡婦、病人などで代表される人々)を赦され、また回復させることを目の当たりにしました。
今日の箇所でイエスさまは十二人を派遣される際、彼らに「汚れた霊に対する権能を授け」(2)ました。イエスさまは十二人に二つのことを命じられています。一つは、神さまを信頼して出て行くことです。イエスさまは「旅には杖一本のほか何も持たず、パンも、袋も、また帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように」(8-9)と言われています。すなわち、「思い悩むな」ということです。エジプトから導き出されたイスラエルの人々は、荒野で昼は雲の柱で、夜は火の柱で、彼らに先立って進んで導かれる神さまを経験しました。もう一つは、伝道の結果に左右されないことです。イエスさまは弟子たちに福音を迎え入れる所に留まり、迎え入れない所を出て行きなさいと言われています。私たちは伝道の結果に左右されがちですが、「父からお許しがなければ、だれもわたしのもとに来ることはできない」(ヨハネ6:65)とあるように、救いは神さまに属されているのです。
「十二人は出かけて行って、悔い改めさせるために宣教した」とあるように、私たちもイエスさまの言葉に聞き従い、この世に出かけて行って宣教しましょう。
ダビデの竪琴
サムエル記上16:14-23
2008年6月8日
まだサウルが王位にいた時に、神さまは羊飼いのダビデをイスラエルの王として選ばれます。神さまによって新しい王が油注がれたことは、イスラエルの民に対する主権が神さまにあることを示しています。
ダビデはイスラエルの王として油注がれましたが、王には似つかわしくない羊を飼うことに忠実でした。既に神さまによって王として認められましたが、まだ公には隠れた形でした。ある日、ダビデはサウル王に呼ばれて、王のさいなまれる魂の傍らで竪琴を奏でて癒します。羊飼い、癒し人というダビデのイメージはイスラエルの王なる神さまの本質を垣間見せてくれます。ダビデの竪琴は羊を飼っている時も、王として油注がれサウルの傍らで慰める時も、同じく神さまの主権を讃美していました。ダビデの竪琴は王なる神さまへの「讃美」を象徴しています。ダビデがどのような讃美をしたのかに思いを馳せながら詩編を読んでみました。詩編には神さまが見えない厳しい現実に対する信仰者の呻きと、その呻きに応えられる神さまへの褒め称えが満ちています。詩編の詩人たちの讃美は、神さまを避けどころとする者は幸いであるという信仰からにじみ出て来るのだと思います。神さまは力を持って人々の上に君臨する王ではなく、ダビデのように羊飼いとして人々を慈しみ、また、苦しみの中の魂を癒される私たちの真の王であります。
私たちはイエスさまが私たちの王として、羊飼いであり、癒し人であることを喜び、各々が持っている竪琴を奏でながら主を讃美していきたいと思います。
イエスの名によって
使徒言行録3:1-10
2008年6月1日
ペンテコステの出来事から始まった初代教会は、イエス・キリストの名を熱心に宣べ伝えました。その働きの一つに使徒たちにより「不思議な業としるし」(2:43)があります。それは生前のイエスさまが人々を癒され、回復へと導かれたお働きを受け継ぐことでした。
今日の箇所はペトロとヨハネが生まれながらの足の不自由な男をイエス・キリストの名によっていやす話です。「美しい門」とは神殿の栄光を表し、毎日人の施しを乞う足の不自由な男は神殿の影を表しています。この光と影とのコントラストは当時のユダヤ教の現実でした。実は、イエスさまはそのコントラストの影のところで、嘆き悲しんでいる人々のもとへ行き彼らを癒され、真の回復へと導かれたのです。初代教会も聖霊の助けによりイエスさまの眼差しで事柄を見始められたことでしょう。二人の使徒は男を「じっと見て・・・・ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい」と言いました。二人の行動はイエスさまが昇天の時「いつもあなたがたと共にいる」という約束の実現です。二人がイエスさまの約束に信頼を置けたのは、イエス・キリストの名こそ私たちが救われるべき唯一の名であり、この名のほかに、人間には救いは与えられていないからです。癒された男は歩き回ったり、踊ったりして全身をもって神さまを讃美しました。
私たちの教会の内外にもこのようなコントラストが存在するかもしれません。私たちがその影のもとで苦しんでいる人々をイエスさまの眼差しで見、イエス・キリストの名によっていやしと慰めを与える働きに励んでいきたいと思います。
燃え尽きない柴
出エジプト記3:1-6
2008年5月25日
モーセの80年間の人生を一言で描写するならば、「寄留者」という言葉が適切でしょう。同胞の苦しみを目の当たりにしながらエジプト王宮で王子としての40年間、さらに殺人者となり王宮とは対極にある荒野で羊飼いとしての40年間は、苦しみや儚さで満ちた歩みでした。その時、神さまはモーセを呼ばれます。
神さまは燃え尽きない柴の間からモーセに声をかけられました。モーセは「どうしてあの柴は燃え尽きないのだろう」と不思議に思います。「寄留者」のように狭間を生きてきたモーセは、まさしく荒野にありふれている何の値打ちもない柴のような存在でした。その柴に神さまの霊を象徴する炎が覆っている光景は、モーセに神さまが共にいて下さり、神さまがモーセを大いに用いられることを意味するのではないでしょうか。モーセはこの突然の神さまとの出会いから、二つのことを教えられているように思われます。一つは、「ここに近づいてはならない」という人間の罪に対する神さまの「否」であります。もう一つは、「足から履物を脱ぎなさい」という神さまへの「服従」であります。神さまは今日も私たち一人一人の人生の中で、燃え尽きない柴の中から神さまの時に私たちに声をかけて下さっています。
わたしたちの常識や経験を脱ぎ捨てて神さまの燃え尽きない力とお働きに目を向けたいものです。柴のようなわたしたちの群れが神さまにますます用いられることを期待し、自分たちの常識や経験を脱ぎ捨てて神さまに従っていけることを切に願います。
神の子とする霊
ローマの信徒への手紙8:12-17
2008年5月18日
ローマ書の7章の最後で使徒パウロは、心では神さまの律法を喜ぶが、肉では罪の法則に従う自分を「惨めな人間」であると嘆いています。しかし、この嘆きは「キリストに結ばれている者」(8:1)であることに目を向けた時に喜びと確信へと変わります。
パウロは神の霊こそがキリストに結ばれていることを証して下さるのだと宣べながら、聖霊に従って生きることを勧めています。聖霊はわたしたちにキリストを主と告白させて神の子とさせる霊です。その働きによって、私たちは神さまを「アッバ、父よ」と呼ぶことが出来ます。「アッバ」という言葉は子どもが親を呼ぶ「パパ、ママ」に当たるアラム語です。ユダヤ人にとって神さまをアッバと呼ぶ行為自体が納得の行かない神に対する冒涜でしたが、キリストに結ばれた者にとっては赤ちゃんが親を無限に信頼するように神さまとの親密な関係を意味します。わたしたちが神さまの子どもであることを聖霊自ら証して下さるのです。すなわち、わたしたちは神さまの豊かさを受け継ぐ相続人であり、キリストと共に受ける栄光のために、現在の苦難をもキリストと共に喜びを持って受けることが出来ます。
パウロは8章の最後に「私たちの主キリスト・イエスによって示された神の愛から、わたしたちを引き離すことは出来ないのです。」と確固たる喜びに満ちています。わたしたちが神さまの子であることを聖霊自ら証して下さることを喜びながら、キリストと共に信仰の歩みを続けたいと願います。
聖霊の賜物
使徒言行録2:1-11
2008年5月11日
今日は教会の誕生日と言われるペンテコステです。昇天する前のイエスさまが言われた聖霊降臨の約束が実現して初代教会が始まった日だからです。
その約束を待望した人々に聖霊が降ってきました。激しい風のような音が聞こえ、炎のような舌が現れました。聖霊は一人一人の上に留まり、一同を満たし、導かれました。旧約聖書で風と炎はいつも神さまの臨在を表します。燃え尽きない柴からモーセを呼び寄せたように、風と炎の中から十戒を与えられたように、神さまは教会を建てられ彼らと新しい契約を結ばれたのです。聖霊降臨の出来事は、イエスさまが福音宣教に出かけようとした時に聖霊が降って来たように、イエスさまによって遣わされる人々を教会として歩み出させる聖霊によるバプテスマであったのです。
天下のあらゆる国々から来た人々が、めいめいの言葉で神さまの偉大な業を聞く奇跡が起こります。これは単に不可思議な奇跡というだけではなく、バベルの塔の出来事以来お互いに理解し得なかった人々が、聖霊の働きによって言語の壁を越えて福音を同じく理解したという一つの大きな回復を意味しています。また「神の民」の概念が、イスラエル民族からキリストを頭とする教会へ移ったことを意味しています。
田代天音さんのバプテスマ式が午後に行われます。聖書勉強会や、バプテスマクラスが聖霊に導かれたこと、また教会のみなさまに支えられ、祈られてきたことを心から感謝します。聖霊は神さまからの贈り物であると同時に、一人一人が聖霊から教会を築き上げる賜物を与えられています。私たちの教会が聖霊によって導かれて歩むことを切に願います。
福音を宣べ伝えよ
マルコによる福音書16:14-20
2008年5月4日
「missio dei(神の宣教)」とは福音宣教が神さまの御業であることを意味しています。教会の宣教は神さまの宣教に与ることであります。
今日の箇所で、復活されたイエスさまは弟子たちに現れて彼らの不信仰をお咎めになります。このイエスさまの叱りから私たちは弱まった弟子たちに対するイエスさまの愛を感じます。次にイエスさまは「全世界に行って、すべての造られたものに福音を宣べ伝えなさい」と命じられます。福音とは神さまの統治によるすべての抑圧からの解放を意味します。イエスさまは、失敗して落ち込んでいる弟子たちの状況を誰よりもよく分かった上で、なお「行きなさい」と命じておられます。イエスさまは弟子たちが自分の弱さや無力さ、状況の良し悪しなどに目をとらわれずに、死からよみがえられたイエスさまに目を向けて福音宣教の第一歩を踏み出すことを望んでいたのです。弟子たちはイエスさまの言葉に従って出掛けて行って宣教します。その時、弟子たちは主が「彼らと共に働き…言葉が真実であることを…お示しになった」(20節)ことを経験します。同様に、旧約聖書の出エジプト記では自分の失敗や口下手などに目をとらわれていたモーセが「あなたの口と共にあって語ることを教えよう」と言われた神さまによって遣わされ、イスラエルの民が神さまによってエジプトから救済されることを体験するのです。
20年前に私たちはこの赤羽の地に遣わされました。主が共におられるとの約束に依り頼み、出掛けて行く教会となることを願います。
主を愛する
申命記10:12-22
2008年4月27日
今日の箇所はモーセがイスラエルの民に、神さまがご自分の民に求められることが何かについて語っているところです。神さまの導きと神の民の頑なさを同時に身をもって経験してきたモーセは、重ね重ね「主を愛する」ことを次の二つのことによって語ります。
第一に、心の包皮を切り捨てることです。これは神さまとの関係の徹底を意味します。割礼とは神さまがアブラハムの子孫を祝福するという約束のしるしです。モーセが言う心に割礼を受けるとは、割礼自体に満足することなく、その割礼を祝福のしるしとして与えられ、成し遂げられるお方を心から信頼することではないでしょうか。私たちの歩みの中でも神さまの主権を認めることが求められていると思います。第二に、寄留者を愛することです。これは隣人と関係の徹底を意味します。寄留者とはその地の法律で保護されない弱者で、モーセ自身も生涯寄留者でした。イスラエルの民もエジプトの国で寄留者でした。モーセは神さまを「人を偏り見ず、賄賂を取らない。孤児と寡婦の権利を守り、寄留者を愛して食べ物と衣服を与えられる」(17-18)と良き裁判官として描いています。神さまは弱者や傷ついた者を無条件的に憐れまれました。私たちの歩みの中でも弱者の立場を考えることが求められていると思います。
2008年度の主題標語は「神さまの望みを生きる教会」(デサロニケ一5:16-18)です。わたしたちの教会が全身全霊で主を愛する時、日々の歩みの中で喜びと祈りと感謝がつき物となることでしょう。
キリスト者の自由
ガラテヤ信徒への手紙5:2-15
2008年4月20日
ガラテヤ地方の諸教会は、割礼を救いの条件と教えるユダヤ人キリスト者たちによって惑わされていました。パウロはこの書簡の前半では信仰義認について、また後半ではキリスト者の自由について熱く記しています。
パウロが語る「自由」とは、律法からの自由を意味します。ユダヤ人キリスト者たちは律法を守ることによって救われると教えていました。彼らの言葉に惑わされている諸教会の人々は、割礼を受けることで救われたという確信を得ようとしたのかも知れません。このような考えは古今東西の教会を通じて見られます。信仰に入ってから自分の行動や、人の行動が救われた者にふさわしくないと判断します。これは自分自身が救われた根拠を自分の行動から見出そうとする誘惑です。しかし、パウロも言っているように、もしそうであれば、キリストは何の役にも立たない方になり(2)、神さまから頂いた恵みも失います(4)。しかし、キリストにより自由を得たからやりたい放題でいいのかという疑問が残ります。パウロは13節で、「この自由を、肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕えなさい」と律法から自由を得られたキリスト者が目指すところを、隣人愛だと示しています。律法から自由になったのになお律法を守るようにと聞こえますが、これは救いによって起こる私たちの応答です。
キリスト・イエスの十字架を見上げながら愛によって互いに仕える教会となることを切に願います。
主、我が牧者
エゼキエル書34:11-19
2008年4月13日
エゼキエルはイスラエルの民と一緒にバビロン捕囚に連れて行かれて、その地で捕囚のイスラエルの民に対して神の御言葉を告げた預言者です。神さまはエゼキエルを通してイスラエルの民との関係を、牧者と羊として宣言されます。牧者が自分の羊の群れを探し出して養うように、神さま自らイスラエルの民を帰還させて良い牧草地で養うことを約束されています。
神さまがご自分の民を養うと約束した良い牧草地はどのような地でしょうか。14節に「イスラエルの高い山々」とあります。食べる物が豊富だから良い牧草地というよりは、神さまご自身が民の牧者となって下さるから良い牧草地なのです。それはまさしく、エジプト脱出後にイスラエルの民が導かれたところが荒野だったことと通じます。荒れ果てているところで神さまは「傷ついたものを包み、弱ったものを強くする」と言われます。厳しく寂しく、何も見えない環境の中で、神さまはわたしたちの牧者となられて命がけで私たちを守ってくださるのであります。その時はじめて私たちには真の休息が与えられます。エゼキエルの預言通りに(23節)イエスさまはこの世に善い羊飼いとして来られました。そしてわたしたちのために十字架上で殺されました。また復活を通してわたしたちに新しい命を与えて下さいました。私たちはイエスさまを見上げることで牧者である神さまを知るようになります。
神さまが自ら私たちの教会の牧者となられて私たちを探し出し、私たちを養ってくださることを覚えて日々歩めればと願います。
新しい命を生きる
コリントの信徒への手紙二4:7-16
2008年4月6日
作家北条民雄は『いのちの初夜』の最後のくだりで「全然癩者の生活を獲得する時、再び人間として生き復るのです」と言っています。これはハンセン病患者の著者が全く新しく生きようとした渾身の叫びです。
今日の箇所で使徒パウロは、人間の弱さを土の器に喩えながらも、その弱くて割れやすい土の器の中にイエス・キリストという宝を納めていると語っています。わたしたちは様々な試練に遭遇してすぐに絶望したり、諦めたりする弱い存在ですが、私たちの内にイエス・キリストが生きておられることが大きな励ましとなります。私たちは自分の弱さに目を向けるのではなく、私たちの内にいるイエス・キリストにこそ目を向けたいと思います。使徒パウロは生きる望みを失うほどの厳しい伝道旅行を「四方から苦しめられても行き詰らず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない」と証しています。パウロにとってそのような苦難こそイエスさまの死を体にまとっていることであり、イエス・キリストの命が自分の中に現れる証であると告白しています。そのようなパウロの信仰には主イエスを復活させた神さまが、自分たちを復活させて下さるという揺らぎない信仰があったと思います。
今月から始まる2008年度の歩みが、わたしたちの弱さの故に落胆することなく、宝であるイエス・キリストの故に与えられている新しい命を生きる年となればと思います。
主の食卓へ
ルカによる福音書24:13-35
2008年3月30日
今日の箇所で二人の弟子は、おそらく師に懸けた期待の敗北感と師を裏切った自分たちの罪責感を持ってエルサレムを立ち去ったと思われます。孤立無援のように思われる彼らの道にイエスさまが付き添っています。
イエスさまと共に歩きながら、イエスさまを知っているつもりで気付かなかった二人のアイロニーは私たちの姿かも知れません。一日中共に歩き、話し合い、聖書を解き明かされても「二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった」です。
二人の弟子がイエスさまに気付いたのは、イエスさまと食卓に着いた時でした。イエスさまがパンを裂いてお渡しになった時、「二人の目が開け、イエスだと分かった」のです。二人はイエスさまとの食卓で遮られていた目が開け、復活のイエスさまに気付きました。二人は生前のイエスさまと共に食卓に着いた時のことを思い起こしたのでしょう。罪深い女性の香油の献げを、幼い少年の五つのパンと二匹の魚の献げを、やがては「これは、あなたがたのために与えられるわたしの体である」と言われた最後の晩餐でのイエスさまの献げを思い起こしたでしょう。まさしく「わたしが命のパンである」(ヨハネ6:35)と言われたイエスさまが彼らのために命を献げて下さったことに気付いたのです。
礼拝をはじめ、個人のディボーション、祈り会などで復活のイエスさまに気付かされていく2008年度を目指して歩みましょう。
生きておられる主
ルカによる福音書24:1-11
2008年3月23日
イエスさまの時代の女性たちと言えば、人数に数えられていなかった上に、証人として効力もありませんでした。一言で云えば、人間以下に扱われていました。
今日の箇所ではそのような女性たちによってイエスさまの復活が伝えられています。女性たちの中にマグダラのマリアという女性が出てきます。彼女はイエスさまから「わたしもあなたを罪に定めない」(ヨハネ8:11)という言葉で救われ、ナルド香油を割ってイエスさまの足をぬぐった人物で知られています。彼女は不幸な人生の真ん中でイエスさまに出会い、人間として受け入れられたことでしょう。しかし、その喜びもむなしく、イエスさまは反逆者として十字架の上で惨たらしく殺されました。それまでのイエスさまの教えや、癒し、福音のすべてが失敗であるかに思われました。彼女がイエスさまによって受け入れられたことも無意味になりかねない状況でした。彼女は悲しみと絶望の中でイエスさまの墓へ行ったのかも知れません。
しかし、イエスさまは罪人の手に渡され、十字架につけられた後、言われていた通りに三日目に復活させられました。これは彼女たちを受け入れられたイエスさまが真理であったことの確証でした。また、彼女たちは貧しく無力でしたが、神の国を所有していたことの立証でした。彼女たちはイエスさまの復活の最初の証人として用いられたのです。
神さまは「力ある者に恥をかかせるため、世の無力な者を選ばれた」(一コリント1:27)お方です。わたしたちの信仰の歩みが今も生きておられるお方に支えられて歩まれればと思います。
平和と栄光の道
ルカによる福音書19:28-40
2008年3月16日
イエスさまは子ろばに乗られて謙遜な姿でエルサレムに登られますが、イエスさまを迎える人々にはそれぞれの考えがありました。
イエスさまが二人の弟子に子ろばを引いて来させたのは弟子たちをイエスさまの働きに参与させる配慮のように見取れます。この子ろばに乗られてイエスさまは十字架での死と復活の第一歩を歩まれます。この姿は旧約聖書の実現であると同時に(ゼカリヤ9:9)、神さまに従うイエスさまの従順な姿を表しています。人間を救おうとする時、イエスさまは子ろばに乗られました。これは生まれた時飼い葉桶に寝かせられた姿と重なり、イエスさまの生涯に貫かれて見られる低くされた神の子として姿であります。そのようなイエスさまを迎えた二つの群れがいました。一つは弟子たちの群れであります。彼らはイエスさまの働きから革命を起こしてローマ帝国を倒してくれる政治的メシアを見ていました。もう一つはファリサイ派の人々です。彼らは弟子たちを叱ってくれるようにイエスさまに願い出ています。イエスさまはご自身を正しく理解していない弟子たちやファリサイ派の人たちを憐れまれました。イエスさまは力を持って平和を得ようとする人々のやり方を否定され、無力で弱い姿で平和と栄光の道を行こうとされていたのです。
今週は受難週です。イエスさまはご自分の命をわたしたちのために献げて下さり、その十字架と復活の御業によって救いを成し遂げられました。イエスさまの受難の道は平和と栄光の道であることを黙想しましょう。
捨てる石から礎の石へ
ルカによる福音書20:9-19
2008年3月9日
エルサレムに入られたイエスさまは人々に譬え話をされます。「ある人がぶどう園を作り、農夫たちに貸して旅に出かけた。収穫の時に主人は収穫を納めさせるために僕の一人を送るが、農夫たちは僕を袋だたきにして追い返した。それから三度も僕が遣わされるが、その都度農夫たちは僕たちを侮辱して放り出した。そこで主人は愛する息子なら敬ってくれると思って自分の息子を送るが、農夫たちはこの息子を殺せば、相続財産が自分たちのものになると思い、息子を殺してしまった。さて、ぶどう園の主人は農夫たちをどうするだろうか。戻ってきて、この農夫たちを殺し、ぶどう園をほかの人たちに与えるに違いない」と。
ぶどう園の主人は神を、ぶどう園はイスラエルを、農夫たちは民の指導者を表します。遣わされた僕は預言者を、息子はイエスさまご自身を表しています。イエスさまに権威を問うているファリサイ派の人々は、主人の主権を否定した農夫たちであります。この譬え話はイスラエルの歴史そのものであります。まもなく起きるイエスさまの苦難と十字架での死は、農夫たちに惨たらしく殺されたように「大工の捨てる石」でしたが、神さまはイエスさまを「礎の石」として復活させられます。すなわち、人間のイエスさまに対する否定を大きな肯定へと祝されたのです。
受難週を迎え、イースターを前に神さまに委ねられている最後の勝利を見上げつつ、「捨てる石から礎の石」となった主イエス・キリストを中心としてしっかり組み合わされて成長する教会を夢見ます。
栄光に輝くイエス
ルカによる福音書9:28-36
2008年3月2日
イエスさまが誰なのかという問いは福音書記者の重要な関心事であり、現代のわたしたちにも問われる問題でしょう。その問いをイエスさまは十字架の死と復活から答えられました。
それから八日の後、イエスさまは弟子たちを連れて山に登られます。弟子たちは栄光に輝くイエスさまとモーセとエリヤを見ました。また「これはわたしの子…これに聞け」という、バプテスマを受けられた時と同様の神さまの声を聞きました。これはイエスさまが十字架の死を克服して復活される出来事の先取りであります。十字架の死ですべてが終わるのではなく、新しい始まりだという神さまの恵みだったのです。弟子たちはイエスさまの復活の栄光を体験しますが、その意味が分からなかったと思います。山の下では悪霊を追い出すことの出来ない厳しい現実に戸惑いを覚えていたからです。イエスさまは弟子たちがご自分の死のために深い絶望を味わうことを知っておられ、弟子たちに降りかかる苦難から復活の希望を持つように望んでおられたのではないでしょうか。復活のイエスさまに出会った弟子たちは絶望を克服して、命がけの伝道者となります。その過程の中で、弟子たちはこの山で見た栄光に輝くイエスさまの姿を思い起こし自分たちが置かれていた厳しい現実から希望を見出すことが出来たと思います。
イエスさまが弟子たちに栄光に輝くイエスさまの姿を見せて下さったように、今も御言葉や周りの弱者を通してイエスさまの栄光を見せてくださっています。祈りながら日々歩みましょう。
心に留められる主
イザヤ書63:7-14
2008年2月24日
「心に留める」と預言者は神さまの恵みを思い起こして、同胞のイスラエルの民に語り告げています。預言者が思い起こして語り告げている神さまの恵みを考えることは、わたしたちを変わらない神さまの恵みに心を向けさせます。
預言者が思い起こしている神さまは、イスラエルの人々を「わたしの民、偽りのない子ら」と言われ、「彼らの苦難を常にご自分の苦難とし・・・彼らを贖い・・・彼らを担って下さった」お方であります。これの背後にある出来事はかつてエジプトで奴隷であったイスラエルの苦しみを神ご自分が救い出したことでしょう。神さまはご自分の民への苦しみを目の当たりにして「わたしは、エジプトにいるわたしの民の苦しみを見、追い使う者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った」(出3:7)とモーセに言われたことがあります。まさしく神さまの思いは産みの苦しみそのものだったように感じられます。
預言者の呼びかけにイスラエルの民は出エジプトでの神さまが「どこにおられるのか」と現実の苦しみに一層目を向けます。神さまがおられるならば、このように滅びに先走る国を放っておくはずがないと嘆いているのです。
神さまの言葉を預かった預言者は胸がちぎれる思いで泣き叫びます。「思いのままに良くない道を歩く民に、絶えることなく手を差し伸べてきた。」「わたしは新しい天と新しい地を創造する。」神さまはわたしたちを心に留めておられます。わたしたちを忘れません。神さまの恵みを思い起こし、語り告げていきたいです。
神の国が来ている
ルカによる福音書11:14-26
2008年2月17日
イエスさまの公の働きの核心は、神の国の福音を宣べ伝えることであります。それはルカがイザヤ書から引用したような「捕われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げる」(4:18-9)働きであります。
今日の箇所でもイエスさまは神の国がすでに人々の間に来ていることを教えるために、口の利けない人を癒されます。しかし、人々はイエスさまがベルゼブルの力で悪霊を追い出したと中傷しています。イエスさまの働きはなかなか理解されませんでした。バプテスマのヨハネすらもイエスさまの働きが理解できず「来るべき方は、あなたでしょうか」と聞くほどでした。イエスさまの働きは当時の人々が夢見ていた政治的かつ革命的メシア像とは程遠い姿だったからです。
イエスさまは人々の無理解に論理的に答えて、「わたしが神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ」(20)と言われました。イエスさまの働きが施されるところに神の国がすでに来ていて、イエスさまの働きを見た人、聞いた人はみな神さまに支配されて、神さまと、隣人と、自分と正しい関係を結ぶようになるのです。
わたしたちが御言葉を読み、また黙想していく時にわたしたちの中に神さまの国が来ています。わたしたちも神さまに支配されて、自分の欲に従って生きるのではなく、「わたしのために身を献げられた神の子に対する信仰によって」(ガラ2:20)生きたいと願います。
主の名を呼び求める
ローマの信徒への手紙10:8-13
2008年2月10日
「主の名を呼び求める」というのは、信じるために最善を尽くす「行為」ではなく、神さまからの恵みに対する「応答」であります。
パウロはローマ書9~11章で同胞のユダヤ人も救われるということを語っています。なぜなら、すべての人々にイエス・キリストを通して神さまの救いが与えられているからです。しかし、ユダヤ人は律法を守る行為によって救われると思っており(自分の義)、キリストを信じることによる救いが理解できませんでした。律法とは救いそのものではなく、神さまの恵み導いてくれる養育係り(ガラ3:24)であり、キリストに案内してくれるものであります。ユダヤ人の自分の義を主張する限り、イエス・キリストが成し遂げられた受肉と復活は無駄になります。パウロは教会の人々にイエス・キリストを信じて神さまと正しい関係に結ばれる「信仰による義」を力説しています。信仰による義とは、不信心なわたしたちをそのままで義とする神さまを心から受け入れて、口で公に言い表すことであります。いわば、お父さんの恵みに気付かされた放蕩息子が「破産宣告」を認めてお父さんのもとに立ち返ることに例えられます。これこそ「心で信じる」、「口で言い表す」という「応答」であります。
「主の名を呼び求める」わたしたちは、神さまから与えられた恵みに対して「応答」し続けていく群れです。そのような応答や告白がわずかなことでも具体的にわたしたちの教会を通して隣人に広がっていくことを願います。
我を憐れみ給え
ルカによる福音書18:9-14
2008年2月3日
今週の水曜日からレントが始まります。レントとはイースターを控えた40日前からイエスさまの受難と復活を覚え、慎んで自分を顧みながらイースターを準備する期間であります。今日の箇所からその姿勢について考えてみましょう。
イエスさまはファリサイ派の人と徴税人との祈りの譬えから、へりくだることを教えられています。これは前の段落のやもめと裁判官の譬えから気を落とさずに絶えず祈るという教えとワンセットと思われます。わたしたちは日々の生活の中で、時には神さまの沈黙に落ち込んだり、時には高ぶって人を見下したりします。そのようなわたしたちにイエスさまは気を落とさずに祈り、またへりくだる人々の間に神の国があることを教えられているのです。徴税人は「主よ、罪人のわたしを憐れんで下さい」と祈っています。へりくだり、神さまの憐れみを求めているこの姿こそ真の信仰ではないでしょうか。神さまがわたしたちの祈りを聞いて下さること、また正しく適えて下さることへの信頼があるからこそ「わたしを憐れんで下さい」と祈ることが出来るのではないでしょうか。この章の最後でイエスさまはご自分の受難と復活を理解していない弟子たちの前で「わたしを憐れんで下さい」と叫び求める一人の盲人を癒し、彼の信仰を褒められました。
わたしたちの教会はイースターを迎えて特別伝道集会を計画しております。イエスさまの受難と復活とにわたしたちの目が開かれることを祈りながらイースターを迎えましょう。「我を憐れみ給え!」
キリストに結ばれた者
コリントの信徒への手紙一1:1-9
2008年1月27日
「キリストに結ばれた者」とはどのような者でしょうか。コリント教会宛のパウロの手紙の冒頭の挨拶から、イエス・キリストによって召された者、豊かにされた者、作られていく者だと学ばされます。
第一に、キリストに結ばれた者とはイエス・キリストによって召された者であります。本文はキリストの使徒として召されたパウロが、キリストによって召されて聖なる者とされたコリント教会宛に書いているものです。パウロという個人も教会という群れも主イエス・キリストに招かれてはじめて存在意義があるのです。第二に、キリストに結ばれた者とは、イエス・キリストによって豊かにされた者であります。パウロは私たちを招かれるイエス・キリストの故に、私たちがすべてのことにおいて豊かにされたと言っています。イエス・キリストはご自分の命を代価として払って私たちを買い取られたからです。命がけで愛してくださる方がいるわたしたちは何も持っていなくても豊かではないでしょうか。第三に、キリストに結ばれた者とはイエス・キリストによって形作られていく者であります。個人も教会も現在は自分と他とを比べながら優越感や劣等感をもつ限界ある存在にすぎませんが、救い主イエス・キリストが主の日まで私たちをしっかりと支えて、非の打ちどころのない者として下さるのであります。
わたしたちは「キリストに結ばれた者」です。すなわち、神の子、主イエスキリストとの交わりに招きいれられた者として日々歩んでいきたいと思います。
恐れることはない
ルカによる福音書5:1-11
2008年1月20日
「恐れることはない」という言葉は漁師のペトロへのイエスさまの招きの言葉です。ペトロは何を恐れていたのでしょうか。また、今日を生きるわたしたちにとってもペトロの持った恐れを抱えていることに気付かされた時、このイエスさまの「恐れることはない」という招きはわたしたちに励ましと力となると思います。
イエスさまは一晩中無駄骨したペトロに近づいて来られて、船に乗られて群衆に教え始められます。ペトロはそのそばで言葉を聞かざるを得ない状況に置かれます。教え終えられたイエスさまはペトロに「沖に漕ぎ出し網を降ろし、漁をしなさい」と言われました。「御言葉ですから」と網を降ろしたペトロの行為が、従順からのものか、反抗を感じつつであるのかは断定できませんが、自分の経験や自尊心を手放さねばならない恐れを感じたに違いありません。さらに、船が沈みそうになるほど魚が取れた時にはペトロはイエスさまの前に立っている自分が罪人であることを自覚させられます。恐れのあまりに「わたしを離れてください」と訴えます。
御言葉通りに生きようとするわたしたちには、自分の経験や自尊心を手放す時、恐れがあることは事実です。またイエスさまを知れば知るほど自分の存在が罪人であることに気付かされます。しかし、そのようなわたしたちの恐れをご存知であるイエスさまは「恐れることはない」と招かれています。イエスさまご自身がわたしたちと共に与えられた人生を歩んでくださることこそが恐れているわたしたちへの励ましとなると確信いたします。
神に心に適う者
ルカによる福音書3:15-22
2008年1月13日
「わたしより優れた方が来ます。その方は、聖霊と火でバプテスマをお授けになり、麦と殻を掻き分けます。」自分をメシアかも知れないと考えている人々にヨハネはきっぱりと言い渡します。ヨハネはイエスさまの道を準備することに生涯を生きました。
ヨハネの言葉どおりイエスさまが現れてバプテスマを受けました。ここではイエスさまがヨハネにバプテスマを受けたかは確かではありません。とは言え、イエスさまのバプテスマが無意味にはなりません。福音書ではイエスさまのバプテスマは聖霊の降りと神さまの宣言に硬く結びついています。バプテスマを受けて聖霊が降って来たのは、神さまの霊の油注ぎを意味しています。旧約時代の王を神さまが立てられたようにこの世にメシアをお遣わしになったことの確証なのです。さらに、開かれた天からは神さまの声が聞こえてきます。「あなたはわたしの愛する子、わたしの心に適う者」。神さまがメシアとして確証されたその方は神さまの独り子です。そして神さまの喜びです。この出来事はイザヤ預言者の「見よ、わたしの僕、わたしが支える者を。わたしが選び、喜び迎える者を。彼の上にわたしの霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。」(イザヤ42:2)という言葉の実現でもありましょう。
神さまはご自分の独り子の死と復活を通してわたしたちに救いを与えられました。その大きい愛を受け入れる信仰によって、わたしたちは神さまの心に適う者となるのであります。
主に寄り頼む者
詩編2:1-12
2008年1月6日
新年明けましておめでとうございます。教会とみなさまの上に神さまの恵みが豊かにありますように。神さまはわたしたちの避けどころであります。神さまはわたしたちの救い主であるからです。詩編2編で詩人は主を避けどころとする人は幸いであると歌っています。
人々は陰謀や反逆を企んで、神さまと神さまが立てられた王に対抗します。詩人はこのような愚かな人間を、1編で「神の道に逆らう者」と看做して「神の道に従う者」が御言葉を口ずさむのに対して、むなしさを口ずさむ者だと言っています。詩人はこのような人間の愚かさに心を痛めながら、「お前はわたしの子、今日、わたしはお前を生んだ」という神さまの定めを述べています。イスラエルの王を立てられ、治めさせるのは神さまであることの宣言であります。そこには人間の救いのために産みの苦しみを厭わない神さまの愛が示されています。神さまに背いている人間、その人間を救おうとする神さまの計画はイエス・キリストを通して成就されるのです。詩人は人々に「畏れ敬って、主に仕え、おののきつつ、喜び踊れ」と呼びかけています。人間の愚かさ、それに対する神さまの怒りと同時に、神さまの救いに目を向けている詩人は、それこそ、主を避けどころとしているのではないでしょうか。
詩編1,2編は詩編150編の序文に当たります。主の道に従う者、主を避けどころとする者として与えられた人生に真剣に応答しながら歩んでいきたいと願います。